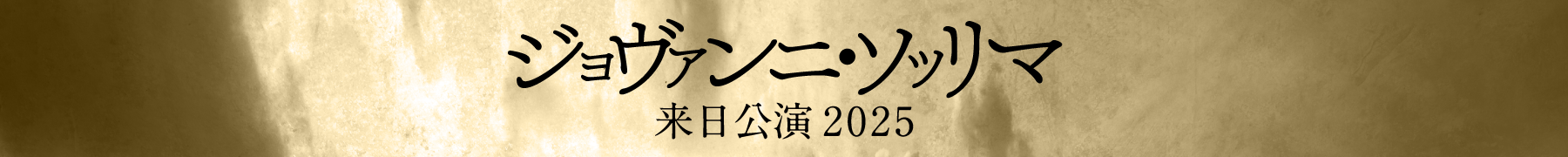2024.09.05掲載
ソッリマの魅力
ソッリマの手にかかると、チェロという楽器は、想像を絶する多彩な音が飛び出してくる、無限の可能性を秘めた、魔法の箱になる。
初めて聴いたときの衝撃は忘れられない。それはさながら、秩序ある人間の集団の中に紛れ込んだ、一匹の美しい野獣のようだった。こんなにも自由で、危険で、あらゆる境界を打破するような――クラシックとロックとジャズと民族音楽が自然に結びついている――規格外の音楽家が他にいただろうか?
その挑戦には限りがない。とりわけ印象的だったのは、本物の氷でできた“アイス・チェロ”によるコンサート・ツアーの最後を、海に楽器を流して溶かすことで終えるという美しいドキュメンタリー映像だった。ソッリマにとってチェロとは、人間と世界全体について考えるための壮大な冒険とロマンのための手段でもあるのだ。
最近のソッリマは、イタリアの大指揮者リッカルド・ムーティとの共演(しかも自作の合唱曲「スターバト・マーテル」)、フランク・ザッパの楽曲を中心にしたコンサート、古楽オーケストラのイル・ポモ・ドーロと共に中近東の要素を取り入れてヴィヴァルディをミックスしたアルバムの録音など、ますますエネルギッシュな展開を続けている。
これまでのソッリマの活動は、どんなにジャンル横断的であろうとも、常にその自由の基盤はバロック音楽と、南イタリアを中心とする地中海の伝統音楽への深い洞察にもとづくものであった。今回のソロ・コンサートでは、バッハの無伴奏チェロ組曲と同時代のバロック作品、そして自らのオリジナル曲を組み合わせたプログラムが予定されているが、いま脂の乗りきっているソッリマの真髄を体験できる内容と言えるだろう。ぜひとも、あらゆる音楽ファンに足を運んでいただければと思う。
文=林田直樹(音楽評論家)
2022.10.12掲載
Anima siciliana ―“命”を奏でるチェロ
《100 チェロ》プロジェクトのコンサートのために来日したジョヴァンニ・ソッリマに密着取材する機会を得たのは2019年の夏だった。インタヴューをおこない、リハーサルをずっと見学し、昼食を一緒にとり、本公演を堪能したその2日間を通して私の心に改めて深く刻まれたのは「命」という言葉だった。つまり、ソッリマは命そのものを奏でる人であるということ、あるいは、彼のチェロは命そのものであるということ。
奏でられる音のひとつひとつ、身振りのひとつひとつ、言葉のひとつひとつにエロスとパッションがみなぎり、生命力が躍動している。もちろんそれは、いたずらにテンションが高い人、という意味ではない。繊細なヴィブラートやピチカート、対話の中のちょっとした沈黙やほほ笑みからだって強烈な生命力が伝わってくる。そしてその生命力は、草木や動物、土、水、風など、我々を取り巻くありとあらゆる存在に宿っていることをソッリマは知っている。彼の眼差しは常に、この世界で輝き、互いにつながり、生かしあうすべての命に注がれているのだ。
9才でチェロを弾き始め、「ベートーヴェンを猛練習した翌日はフランク・ザッパを自由に弾く」ような少年だったソッリマは、常に、ボーダーを越え続ける旅人だった。民族や人種のボーダー、文化のボーダー、ジャンルのボーダー、そして時間のボーダー…。 だから、彼のコンサート・プログラムには、作曲家名としてバッハやベートーヴェンやドヴォルザークなどと並んでピンク・フロイドやレナード・コーエン、メタリカといった名前も当然のように並ぶ。また、彼の自作曲には、アフリカやアラブやインドやバルカンの音楽、ジプシー音楽、ケルト音楽など世界中の伝統音楽/民俗音楽のエッセンスがつまっている。太古よりさまざまな民族が去来し、いくつもの文化が混交、堆積してきた地中海の交差点シチリアで生まれ育ったソッリマにとっては、異文化の混交も、そこから生まれる新しいハーモニーも、ごく自然のことなのだ。生まれながらの“世界人”としての彼の目は、いつだってこの地球という星全体を見つめている。
チェロ1本だけを携えてやって来るジョヴァンニ・ソッリマ。しかしそのたった1本のチェロと Anima siciliana(シチリアの魂)は、私たちに世界の広さと多様さを、無数の生命の脈動と輝きを体感させてくれるはずだ。
文=松山晋也(音楽評論家)