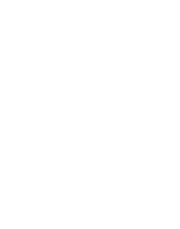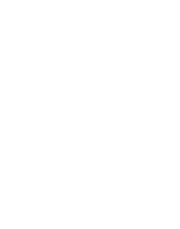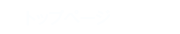
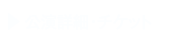
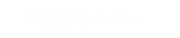
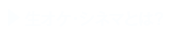
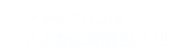

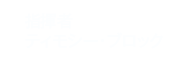
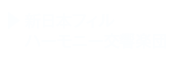
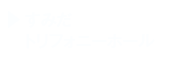

|
|
■チャップリンの名言から、その魅力を紐解く
●「トーキー(発声映画)は、パントマイムという史上最古の芸術を損なっている。静寂に潜む偉大な美を破壊し、スクリーンから意味を奪い取っている」
かつてチャップリンの映画は、1000人から2000人を収容する大映画館で楽しむ一大エンタテインメントとして上映されていた。年齢や性別や国籍を問わず、大勢の観客が映画館というひとつの空間に集まり、スクリーンに映し出されるチャップリンのコミカルな演技に笑い、その裏に隠された悲しい物語に涙した。そういう映画体験を可能をしたのは、チャップリンが台詞のないサイレント映画という表現形式にこだわり、パントマイムで人間の喜怒哀楽を完璧に表現したからだ。1920年代の終わりにトーキー技術が発明され、映画が音を持つようになってからも、チャップリンは最後までトーキー映画に抵抗し、サイレント映画にこだわった。しかもチャップリンは、言葉なしに感情を伝え、物語を伝えるためには一切の妥協を許さなかった。『街の灯』では、盲目の花売り娘をリアルに表現するため、敢えて演技経験ゼロのヴァージニア・チェリルをヒロイン役に抜擢。その彼女とチャーリーが初めて出会う、たったひとつのシーンを撮るために、なんとチャップリンは360日以上の撮影日数と340回以上のテイクを費やし、納得のいくまで撮影を繰り返す完璧主義を貫いた。だからこそチャップリンの映画、とりわけ『街の灯』は、80年以上の時を隔てた現代でも古さを全く感じさせない、永遠の輝きを放っているのだ。
●「人生は、恐れなければ素晴らしい。人生に必要なものは、勇気と想像力と少しのお金だ」
ロンドンのヴォードヴィル芸人の息子として生まれたチャップリンは、幼少期に両親が離婚、しかも精神を病んだ母親が病院に収容されたため、路頭に迷い、極貧生活を余儀なくされた。孤児院を脱走し、万引きを働き、ありとあらゆる職業を転々としながら、決して人生を諦めなかったチャップリンの個人的な体験は、彼がのちに作り上げた映画のほぼすべてに反映されている。浮浪者チャーリーを主人公にした映画、とりわけ『街の灯』で描かれているのは、どんな逆境にもめげず、困難を克服しながら懸命に生き、収入を得ようとする人間の物語だ。ようやく見つかった“職業”が、たとえ都会の清掃夫や八百長ボクシングの拳闘士でもあっても、チャーリーはそれをまたとないチャンスと捉え、慣れない“職業”をこなそうと懸命に努力していく。愛する盲目の花売り娘が、もう一度視力を回復できるなら……。そんなチャーリーが悪戦苦闘をくり返す姿は、チャップリン自身の言葉を借りれば「人生はクローズアップで見れば悲劇、だがロングショットで見れば喜劇」。誰もがバラ色の人生を送っているとは言えない21世紀の現代だからこそ、チャップリンが映画の中で描いた人間の生きざまは、私たちの心に強く迫ってくる。
●「チャーリーにはいろんな側面がある。浮浪者、紳士、詩人、夢想家、孤独な人、みんなロマンスと冒険に憧れているんだ」
山高帽にチョビ髭、ヨレヨレのジャケットにドタ靴とステッキ。衣裳部屋に偶然あった、ありあわせのコスチュームから生まれた浮浪者チャーリーは、1914年の『ヴェニスの子供自動車競争』から1931年の『街の灯』まで、ほぼ一貫してチャップリン映画の主人公であり続けた。珍妙な服装をしたチャーリーが、現代に至るまで息の長い人気を獲得している理由は、単に見た目が可笑しいからではない。チャーリーが社会的弱者の気持ちを代弁し、庶民の味方として活躍を繰り広げるからだ。決してイケメンではないし、背も高くないし、社会的にも経済的にも弱い立場にあるかもしれないが、チャーリーはつねに美しい女性に恋心を抱き、警官や上司の理不尽な支配には思い切って反抗し、軽やかな身のこなしでダンスや楽器演奏を披露し、紳士としての振る舞いを忘れず、「きっといつかは自分も幸福になれる」と希望を胸に抱き続けている。どんな人間も、人間らしく生きる権利はある。その素晴らしさ、大切さをさりげなく伝えているから、チャーリーは今も世界中で愛されているのだ。
文:前島秀国(サウンド&ヴィジュアル・ライター)
|
|





|
|
|
|