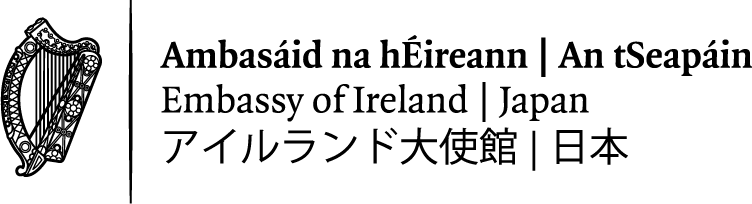東京・赤坂の草月ホール。ステージ奥には天井から40mもの巨大な白い布が吊り下げられ、周囲には流木などを使った樹木のオブジェが配置されている。この舞台の設えからも、この公演が特別なものだということが伝わってくるようだ。
リアム・オ・メンリィ特別公演『螺旋の渦〜青柳』。タイトルにある『青柳』とは、現在NHKで放送中の連続テレビ小説『ばけばけ』のモデルとなった、小泉八雲ことラフカディオ・ハーンの代表作『怪談』に収録された、日本の古い民話を元にした物語。若い武士と、青柳と名乗る若い娘、実は柳の木の精の化身との、現世と異界を超えた哀しく儚い悲恋を描いて人気が高い。
八雲がこうした日本の不思議な民話や伝承を収集し『怪談』を書くまでに強く惹かれた背景には、あの世とこの世、死と輪廻、様々な妖精や精霊たちが常に身近に感じられる数多くの不思議な物語を古くから伝えてきたケルト文化の国、アイルランドで幼少期を過ごした影響がとても大きく、アイルランド人と日本人との間に、「見えないもの」に対する深い敬意と関心、共通した精神性を感じていたからに他ならない。
公演は2部構成。第1部「Tokyo Encounter」では、カナダ・オタワヴァレースタイルのアイリッシュダンスの達人たち、ザ・ステップクルー・トップ3withダン・ステイシーや日本人アーティストも加わって、リアムが得意とするケルト音楽の数々を繰り広げた。
休憩を挟んで、いよいよ第2部「青柳」が開幕。
暗いステージから、静寂を破ってまず響いてきたのは「ヒュウ〜〜ン」という不思議な音色。アグレッシブなチェロ奏者、坂本弘道が演奏するミュージカル・ソウ。刃のない西洋ノコギリ形の鉄板をたわませながら弓で弾く楽器。それはまさに音で聞く「幽玄」そのものだ。
再び静寂の中、そっと語りかけてくるような優しいタッチでリアムがピアノを弾き始める。最初の曲は『ブリジッド・オー・モリー』。最新アルバム『プレイヤー』にも収録された、アイルランド伝統音楽の中でも特に美しく哀愁にあふれたメロディと言われるスロー・エア。恋人を失った若い男性が、彼女への尽きない想いを自然の美しさになぞらえて歌う哀しい恋歌だ。
舞台奥の白い布に、「言葉」が投影されていく。
「青柳」
雪の荒れた地を歩く
寂れた村
君に逢う
「青柳」
遠い昔、
人々は自然の只中で生きていた
木々は、天と地を結ぶ架け橋
青柳」は
この世とあの世を結ぶ
樹木の妖精
全ては樹木から生まれた
文:川島恵子
切なく深く響くリアムのボーカル、それに寄り添う美しいピアノとミュージカル・ソウの幽玄な対話が、舞台から波紋のように広がっていく。
だがこの公演は、「青柳」の物語の音楽による再現を目指してはいない。背景に投影された言葉も、物語の世界観を伝えるものにすぎない。八雲がこの物語に込めた思い。ケルト文化と日本文化が共通して精神の根源に持っている自然と樹木への畏怖と崇拝、「あの世とこの世」「見えないもの」への深い敬愛。そうした想いに共感した、アイルランドと日本の優れたアーティストたちが、樹木へのオマージュと、失われて行くものへの鎮魂のレクイエムを、一夜限り、まさに一期一会のパフォーマンスで伝える渾身のセッションなのだ。
2曲目は『エヘネ』。リアム作曲の最新アルバム収録曲。題名は彼の母親の名から。母の慈悲深い愛を歌う、大地の遥か奥底から聴こえてくる祈りの歌のような低音の旋律が、荘厳でスピリチュアルな響きでホール全体を包み込んでいく。
そしてまた、「言葉」が投影される。
ある日、「青柳」が伐採された
愛する日々が消えた
樹木の精霊に捧ぐ
レクイエム「青柳」
文:川島恵子
加えて投影されたのは、公演フライヤーにも使われたリアムが描いた柳の木、「青柳」の絵だ。
舞台に能楽師囃子方、高安流大鼓方の名手、佃良太郎が大鼓を持って袴姿で登場。スピリチュアルなケルトの旋律に、能楽の掛け声と、大鼓の硬質な音が加わってくる。それは青柳が生まれ育った深い山里を思わせる木霊のようにも聴こえる。
ケルトの音楽と、日本の伝統音楽との出会い。ぶつかり合うのではなく、互いに共感、融合しあって、どこにもない音楽が創り出されていく。
東洋的な響きを持ったスペイン音楽を思わせる哀愁を秘めた旋律。リアムの繊細なピアノソロから始まる3曲目は『ア・ラヴ・トゥ・アラン・カリグ』。あの岩場にいたのか? という題名を持つ、愛しい人に密かに会いにいくことを歌った、最新アルバムにも収録されているアイルランド伝統音楽の名曲中の名曲だ。
リアムのピアノも、次第に左手の強いタッチの低音が音楽を雄弁に主導するようになり、テンポが少しずつ上がっていく。「いょほおーっ、カーンッ!」掛け声とかん高く硬質の大鼓の音はさらに勢いを増し、リアムの歌のゲール語と日本語の掛け声が激しく響き合い、せめぎ合う。
旋律が渦を巻くように最高潮に達すると、一転、ステージに静寂が訪れる。再びリアムの繊細なピアノ。それをインドの民族楽器、タブラ奏者のユザーンが、音程の付いたリズムでそっと支える。
ここに静かに登場したのは、ダンサーのO B A。手足の細かい動きが、全身へとしなやかに広がって大きなダンスになっていく。植物が地面から芽吹き、成長していくような生命力にあふれた踊り。
ダンサーと同時に、庭師としても活動しているOBA。常に植物、樹木、自然に接している彼だからこそ表現できる植物の命と心が見えてくる。
そのダンスの動きと呼応するように、リアムのピアノ、大鼓、タブラ、チェロは、阿吽の呼吸で絶妙のセッションを繰り広げていく。
OBAは一人で踊っているのに、若者と青柳、二人の幸せな愛の日々を描き出す。しかしある日突然、青柳は倒れ、若者の腕に抱かれたまま消えてしまう。深い悲しみと強い心の痛み、チェロのピチカートとタブラの哀しい音色が寄り添う。
慟哭の表情が、手を合わせて祈りを捧げる姿に変わっていく。ピアノ、ミュージカル・ソウ、タブラが奏でる鎮魂のレクイエム、祈りの音楽の中をゆっくり、ゆっくりと歩みながら、O B Aはステージから静かに消えていった。
アルバムでは18分を超える大曲。リアムがピアノの最弱奏で奏でる、深い悲しみの和音がささやくように響き、そして、長い、長い静寂。深い余韻を残して、公演は終わった。
日本人とアイルランド人の心を結んだ小泉八雲の「青柳」の世界を、アイルランドのリアムと日本の才能あふれるアーティストたちが互いに共感し、心を一つにして音楽と向きあったたった一夜だけのコンサート。まさに一期一会の贅沢なセッションを体験できたのは、本当に貴重だった。