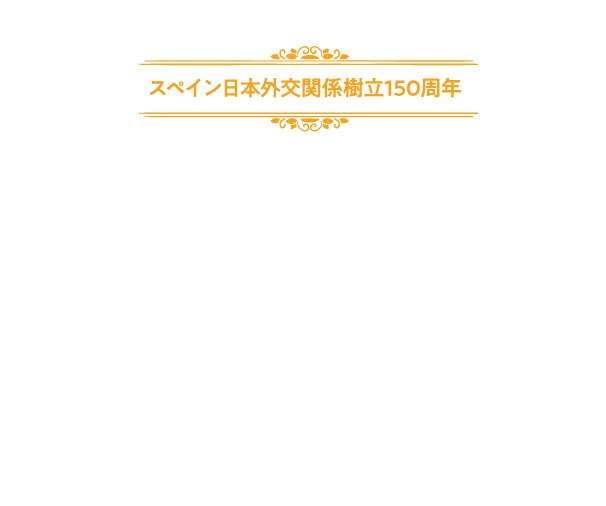
色彩とリズムの奔流。カニサレスのさまざまなスタイルの演奏を聴いた後で、ふと気づくと、いつもそんなことを頭の中で考えている。ギター一本で表現できることの極限。そんなフレーズも脳のどこかをかすめる。フラメンコ・ギターという世界で素晴らしい演奏を聴かせてくれるだけでなく、クラシックのジャンルでも活躍できるのは、やはり基礎的な能力が高いからだが、それだけでもないと思う。まだそのすべてを聴いてはいない、そんなことも思う。それが私にとっての「現在のカニサレス」である。
カニサレスの存在は、まずパコ・デ・ルシアのグループでのツアーなどで日本でもおなじみになったように思う。その後、自分のグループで独自の音楽世界を拓きつつ、たとえばサイモン・ラトル指揮ベルリン・フィルとマドリードの王立劇場で「アランフェス協奏曲」を共演し(2011年)、さらに日本の音楽ファンに近い存在となった。2013年には「ラ・フォル・ジュルネ」音楽祭に参加。私は、ナントでも東京でも彼の演奏を聴くことができたけれど、どの演奏会も素晴らしく音楽的な瞬間の連続で、まさに息の継げないような美しい時間だった。とくにカニサレス自身が書いたオリジナル曲の魅力は、フラメンコ、クラシック、あるいはジャズ、フォークロアなどの垣根を超えて、すべての人の心に訴えるものだと思った。
カニサレスのギター音楽の魅力は、その音色の多彩さ、和声の豊かさ、そして彼の心、イマジネーションから生み出される音楽的アイディアの広がりにあると思う。フラメンコの伝統的なリズムに乗せて、まるでドビュッシーのような和音が煌めく。その時に、私は一瞬時間を忘れて、他の世界に連れて行かれるような感覚を味わった。その音楽を味わった多くの日本の音楽ファン、そしてギタリストたちも、カニサレスの音色に驚嘆していた。
カニサレスはこれまでにソロの録音をたくさんリリースしているが、その中にはアルベニスの作品、そしてグラナドスの傑作『ゴイェスカス』のギター編曲版など、スペインのクラシック作曲家の作品集も多い。それらはピアノや管弦楽でも、表現する時にテクニカルに難しい作品が多いのだが、カニサレスの手にかかると、まるですべてが簡単になる魔法をかけられたかのように、ギターという楽器にぴったりの作品に仕立て直されるのが驚異的である。
今回のカニサレスの来日公演は、彼のカルテットによる演奏だが、カニサレス自身の言葉によると「フラメンコはまさに会話で、その中に感情のやりとりがあることが大事だ」と。それはすべての音楽について言えることだろうし、その基本があるからこそ、彼の音楽が私たちにも伝わってくるのだろうと思う。
そのボーダーレスな魅力を証明する出来事を、ひとつだけ例をあげて紹介しよう。それはラ・フォル・ジュルネ・オ・ジャポンで私の知り合いが体験した出来事だ。あるホールでコンサートが始まるのを待っていると、後ろの席から男の子の声がした。「今度もカニサレス、出るの?」。おそらくその男の子は前のコンサートでカニサレスの演奏を聴き、とても感動したに違いない。「ねえ、カニサレスは?」と何度も男の子は母親に聞く。少年をも魅了してしまうカニサレスの音楽の魅力、それこそが本物の音楽の証明ではないだろうか?
私たちはカニサレスを、また日本で聴くことができる。なんと幸せなことだろう。その男の子もきっと聴きに来てくれるに違いない、と私は確信する。
片桐卓也(音楽ライター)
『パコ・デ・ルシア 灼熱のギタリスト』の原題には『ラ・ブスケダ(La Busqueda)』と副題が付いている。日本語にして、探求の意だ。この映画はパコ・デ・ルシアの、ギタリストとしての人生を追ったドキュメンタリーだ。
しかし同時に、パコの実子である監督のクーロ・サンチェスが、自分自身の人生を探求したものでもある。映画制作を通じて、世界的なギタリストであり、10代のうちに離れて暮らすことになった父でもあるアーティストと最期の4年を共にすることで、クーロの心に何かが満ちていった。我々はその過程を、この作品を通じて追体験することができる。
フラメンコギターを手にした人は、誰もがパコ・デ・ルシアになりたいと思っている。パコは1947年に生まれ、67年のソロアルバムリリース以降、留まることなく快進撃を続け、『二筋の川』(74)で30万枚の大ヒットを飛ばした。『アルモライマ』(76)収録の「広い河」もヒットとなり、6人のバンド編成であるセクステットを結成、そして国際的スターにのし上がることになった、スーパーギタートリオの結成へと突き進む。それによりパコは、世界屈指のフラメンコ・ギタリストとして、唯一の存在へとなっていったのだった。
さて、現在最も世界的に活躍しているフラメンコ・ギタリストは、フアン・マヌエル・カニサレスと言う。カニサレスは誰もが憧れるパコと10年もの間、世界ツアーを共にした非常に優れたギタリストだ。2016年5月にはパコの葬儀が執り行われた国立音楽堂で、パコに捧げるギター協奏曲『アル・アンダルス協奏曲』を初演した。初演を指揮したジョセップ・ポンスが「クラシック・ギター界において、アランフェス協奏曲の初演以来の大きな出来事だった」と演奏後に語った名演は、スペイン国営ラジオを通じて、ここ日本にも届いた。
カニサレスは、クラシックとフラメンコの両方に精通することで、類を見ない存在感を発揮する。1991年に、世界ツアーをしていたパコが名曲『アランフェス協奏曲』をフラメンコ・ギタリストとして初めて録音したが、このときのB面に収録されたのが、共に世界を回っていたカニサレスが編曲した『イベリア組曲』だった。その20年後の2011年、カニサレスもまた、ベルリン・フィル(指揮:サイモン・ラトル)との共演で『アランフェス協奏曲』を弾いた。今日の世界的な活躍は、この傑出したアランフェスの快演がもたらしたものなのだ。
初のクラシック曲の編曲となった『イベリア組曲』、大輪の花を咲かせた『アランフェス協奏曲』、そして他ならぬパコに捧げた『アル・アンダルス協奏曲』。パコ・デ・ルシアから芳醇な栄養を吸収し、今まさに二色の輝きを放ち躍動するカニサレス。その活躍を見逃してはいけない。
なお、1989年に若き日のカニサレスが所属していたユニット〝イベリア〟の唯一のスタジオ・アルバム『フラメンコ・チャレンジ』が、この7月に日本リリースされる。パコとツアーを回ることになる直前の活動を収めた貴重な演奏だ。25年の歳月に想いを馳せてみたい。
小倉泉弥(月刊パセオフラメンコ編集長)

あらゆる演奏家にとっての理想とは、いま生まれて来たばかりであるかのような感激と生命力をもって、歴史に残る名曲を鮮やかに、みずみずしく弾くことであろう。
現代スペインの宝ともいえるフラメンコ・ギタリスト、カニサレスは、そうした理想を求める人であれば、どんなジャンルの愛好家であろうとも、決して聴き逃してはならない重要な存在である。
なぜ、あのサイモン・ラトルがベルリン・フィルとのロドリーゴ「アランフェス協奏曲」のソリストにカニサレスを招き、そのコンサートが今も語り草となるほどの反響を巻き起こしたのか?
その記録映像を観れば、誰もが衝撃を受け、カニサレスが世界的に注目される理由を即座に納得するに違いない。
まず第一に、作曲家が楽譜に書いたことを忠実に再現するという次元を遥かに越えた、妖艶で官能的な音のかたち。それはもうクラシックという枠を越えたものだ。偉大なパコ・デ・ルシアの影響から出発し、ジャズやロック等の様々な分野からもこれまで幾多も共演を懇請されてきた、フラメンコの伝統と生命を持つギタリストならではの強烈な即興性。誇り高いエロス。それがオーケストラと融合したときの素晴らしさ。
第二に、リズムに対する命がけといえるほどのこだわり。かつてカニサレスは「いいリズムを作れるかどうかが大切なんだ」と述べたことがあった。本当に「いいリズム」とはどういうリズムのことを言うのか? フラメンコの源流を追求し、新たな実験にもチャレンジしてきたカニサレスだからこそ提示できる世界がそこにはある。
カニサレスにとって、リズムとは、ただの伴奏ではない。それは、励ましであり、思いやりであり、支えであり、関心と興味であり、牽引とリードであり、抑制と興奮のダイナミズムであり、皮膚と骨格と筋肉であり、冷静から燃焼への爆発的なプロセスであり――友情と愛と人生そのものである。
カニサレスの使っているギターは、フラメンコとクラシックのハイブリッドになりうる特注の楽器である。そして彼自身もまた、楽譜を深く読み、人から人への伝承芸術であるフラメンコにも通じている――まさに特別な存在なのだ。
そのカニサレスだからこそ演奏しうるロドリーゴの名曲「アランフェス協奏曲」がいよいよ日本でも聴けるともなれば、これは足を運ばずにはいられない。 今回の来日公演では、最近素晴らしいレコーディングを残したファリャの作品集も演奏される。スタジオ・セッションと多重録音によって、管弦楽やピアノからの緻密なギターへの再現を行ったCDのときとは違い、ライヴではどのような新しい解釈を見せるのか興味をそそられるところだ。自らのフラメンコ・カルテットのオリジナル曲ともども、神業のようなリズム・アンサンブルと踊りの要素を加味したカニサレスの音楽世界が総合的に体験できるという意味で、絶好のチャンスがついに訪れる。
林田直樹(音楽ジャーナリスト・評論家)