|
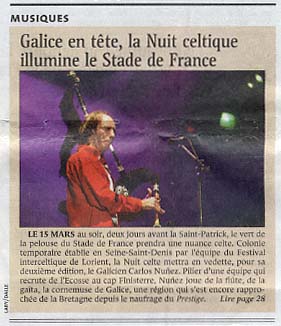 ル・モンド紙にカルロス・ヌニェス登場 ル・モンド紙にカルロス・ヌニェス登場
仏「ル・モンド」紙(2003.3.15)より
「La Nuit celtique (ケルトの夜)」
パリ郊外の巨大スタジアム「スタッド・ド・フランス」が光に包まれる夜
スターは、ガリシアのカルロス・ヌニェス。
3月15日、ケルトの祝祭日:セント・パトリックスデイを2日後に控え、スタッド・ド・フランスの芝生が、ケルト・カラーに染まる。
パリ郊外セーヌ・サン・ドニのスタッド・ド・フランスを会場に、ロリアンのケルト・フェスティバルのスタッフによる<ケルトの夜>は、第二回の今年、ガリシア出身のカルロス・ヌニェスを看板アーチストに選んだ。
今回、スコットランドからブルターニュまで、各地から集合したケルトのミュージシャンの中心的存在のカルロス・ヌニェスが演奏するのは、フルート、そして、ガリシア地方のバグパイプであるガイタ。昨年11月、ガリシア地方沖で起こったプレスティージュ号沈没漏油事故以来、ガリシア地方とブルターニュ地方の絆は、よりいっそうの強まりをみせる。
ガリシア〜スタッド・ド・フランスで輝きを放つケルト銀河系のキラ星
あるディナーの席でのこと。ガリシア自治州知事のマヌエル・フラガが「ケルト文化の存在」に疑問を唱えた。フラガは、以前フランコ独裁政権の情報観光相を務めた経験をもつ90歳の長老。彼自身もガリシアの北部に位置するヴィラルバの出身。この村は、人気アーティスト"マヌ・チャオ"の父方の故郷でもある。そのマヌエル・フラガが、ブルターニュ地方、ガリシア地方、アイルランド、スコットランド、アストリア地方をひとつのケルト文化と位置づける説に対して「科学的に実証されているわけではない」と言い放ったのだ。
それに対して、ガリシアのヴィゴ出身で、フルートとガイタのミュージシャンであるカルロス・ヌニェスが反論する。「サンティアゴ・デ・コンポステーラの巡礼に関する全てのことが実証されているというのですか。されていません。でも、素晴らしい神話ではないですか!」
歴史的根拠から言えば、1131年にサンティアゴ・デ・コンポステーラを目指したエメリック・ピコーの巡礼の方が、ガリシア地方のケルト文化説に比べて、より信憑性を持つのは確かであろう。しかし、ラモン・チャオ(マヌの父で、ジャーナリスト)は語る。
「ケルト文化の類似性は否定できない。伝説にしても、信仰にしても、料理にしても、それにもちろんバグパイプの存在。確かに、科学的には証明されていない。でも美しい話じゃないか。私が自分をケルト民族だと感じるのは、美しいかどうかの基準に拠っているね」
いずれにせよ、セント・パトリックス・デイを祝う3月15日、第二回「ケルトの夜」を機に、ガリシアを始めケルト文化圏の諸国が、スタッド・ド・フランスで一堂に会する。「ケルトの夜」は、ロリアンの国際ケルト・フェスティバルの運営による民族的巨大イベントだ。今回のメインスターは、カルロス・ヌニェスを筆頭に、ブルターニュのアラン・スティーヴェル、アイルランドのシネイド・オコナーの3人。シネイド・オコナーはロリアン・フェスティバルにも参加している。ロリアンのケルト・フェスは、初回以来、国境を越えた同胞的連帯をモットーに掲げている。ダン・アル・ブラース、アラン・スティーヴェル、ザ・チーフタンズのメンバー:パディ・モローニといった古参アーチストに、よりロックンロールのスピリットを感じさせるカルロス・ヌニェス、ブルターニュのシンガー、ドゥネ・プリジョン(Denez
Prigent)といった若いミュージシャンが合流している。
1994年にダン・アル・ブラースの監修で発売されたアルバム「ケルトの遺産〜ケルト・ヘリテージ」が、ケルトの文化的統一ムーブメントを決定づけた。現在、このアルバムはミリオンセラーを記録しているが、そこにはまだガリシアや、アストリアの影はない。
2002年の終わり、ガリシア地方沖で勃発したプレステージ号沈没による重油流失事故を機に、ブルターニュとガリシア両地域の連帯は深まる。ロリアンのケルト・フェス運営委員会が発行する季刊誌は「同胞ガリシアの人々へ」というタイトルで、ブルターニュ地方とガリシア地方の連帯に言及している。
カルロス・ヌニェスは、事故勃発当時、最新アルバム『絆〜ガリシアからブルターニュへ』のレコーディングのためブルターニュにいた。12月、彼は友人と共にガリシアに戻る。そして、彼の町・ヴィゴにバスで駆けつけたジル・セルヴァ、ダン・アル・ブラースをまじえ、チャリティ・コンサートが開かれた。それは普段の彼らの思いを反映するごく自然な行動だった。彼らにとって、ガリシアやブルターニュの海と山の豊かな自然は何としても守るべき大地なのだ。
カルロスがアポの場所に選んだマドリードのレストランは、Rianxoという町の名をレストラン名にしている。 Rianxo からは、メキシコに向けて多くの移住者が海を渡った。レストランのシェフの息子は、伝統的ハープを製造するために郷里に戻ってきた。シェフが自慢のタコや魚料理をふるまう中、ガリシアの白ワイン・アルヴァリーノのグラスを片手に、カルロスが音譜風のサインに応じている。ここでは、みなが胸にシールをつけている。赤をバックに黒い重油をモチーフにしたアンチ海洋汚染のシールには、<もう二度とごめんだ>という文字が見える。
ロングヘア、黒い服に黒いメガネ。32歳のカルロスは、ケルト文化の理想的形の再構築にに尽力するロリアンの人々に感謝を込めて、ロリアンのケルト・フェスティバルのたびにあふれんばかりの若い活力を提供する。このフェスティバルは1970年代の初頭に端を発するが、カルロスが参加したのは1984年で13歳のとき。当時すでに一流の腕前を見せていた彼は、以来フェスの秘蔵っ子となり、スペインにおいては、伝統楽器のミュージシャンとしては珍しい名声を勝ち得ている。
『スパニッシュ・ケルトの調べ』(1996)、あるいは『アモーレス・リーブレス』(1999)のアルバムのセールスは参加アーチストの知名度に比例するかのように、うなぎ昇りの数字を記録した。錚々たる顔ぶれのゲストアーチストは皆、カルロスの友人でもある。ライ・クーダー、リンダ・ロンスタット、ロス・ロボス、ザ・チーフタンズ、リュス・カザル、カルメン・リナレス、ビセンテ・アミーゴ、ロジャー・ホドソン(元スーパートランプのボーカル)などなど。
最新作『絆〜ガリシアからブルターニュへ』では、ダン・アル・ブラース、アラン・スティーヴェル、バガッド・ドレ、ジル・セルヴァ、イーリアンパイプのリアム・オフリン、ヴィオラ・ダ・ガンバ奏者のジョルディ・サヴァル(カタロニア出身)が参加している。
帰郷の機会に、カルロス・ヌニェスは、アラン・スティーヴェルをガリシア地方の村落に案内した。その村々では、どの家にもhorreo(石でできた納屋)がある。その片隅にはカトリックの十字架、もう片方には古代祭儀で生産力の象徴として崇められた男根像が祭られている。カルロスはその後、ブルターニュに「シトロエン号」で戻った。その船は、ヴィゴに自動車を運び込み、ブルターニュ地方のサン・ナゼールにガリシア地方のスレートを運搬する商船だ。
ガリシア人とはいったい何者か?
カルロスは答える。「階段ですれちがった時、昇っているのか、降りているのわからない人間のことさ」
マヌエル・フラガは、フランコ政権下の要人であった頃、決してガリシア語を話そうとはしなかった。フランコもまたガリシアのフェロルで生まれた人間であったが、同様であった。今、90歳を越えるガリシア自治州の長老フラガはガリシア語を話す。ガリシア語はスペイン語同様、国の公用語になったのだ。
「そのことは制度的な変化をもたらした」とカルロスは語る。
「以前はレジスタンスを象徴していたガリシア語が、突如として制度として義務づけられる言語に変わってしまった」
それはほとんど滑稽とも思える変化である。
カルロスは、お上から押しつけられる芸術、オフィシャル・アートに不信感を抱く。
フランコ政権下にはフラメンコがスペインの民族性を代表する芸術としオフィシャル化されたが、彼は自分の中のわだかまりを抑えて、フラメンコのミュージシャンとも交流しなくてはならない時期があったという。政府による文化のオフィシャル化は、スペインだけではない。アルゼンチンのタンゴ、ポルトガルのファドなどが、保守右翼政権に利用された。
自治州として自治権を得た今、ガリシアは植民地コンプレックスから脱却したに違いない。では、ブルターニュ地方の人間はどうか?
「ブルターニュの人達にとっても、スタッド・ド・フランスに参加することは必然的な欲求だったんだ」
彼らは自尊心から、歴史上、女王の警備隊として1度たりとも仕えたことのない人々であるが、今では、マクロ・ミュージック、つまり壮大なスケールの音楽を創造している。バガード(バグパイプ演奏団)は飛躍的な進歩をみせ、ラッパ奏者も一級の腕前を持つようになり、シンガー達もますます洗練されてきている。
しかしgwerzグウェルス(哀歌)はいつも孤独にむせび泣く。ガリシアの哀歌モリーナmorrinaも然り。グウェルスやモリーナといったケルトの哀歌に共通する無国籍者、疎外者達の物悲しい想い(シネイド・オコナーはそれを歌い続けているのだが)もまた、この巨大スタジアムで確認すべきことのひとつであるに違いない。

|

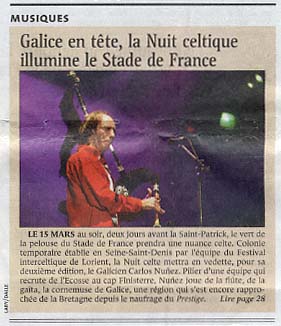 ル・モンド紙にカルロス・ヌニェス登場
ル・モンド紙にカルロス・ヌニェス登場